見せたいものがあると言って七燈は夕鶴を宴の席から連れ出した。どうしても驚かせたかったので彼女には目を瞑ってもらい、その手を七燈が引いて山を登った。
見せたいものがあると言って七燈は夕鶴を宴の席から連れ出した。どうしても驚かせたかったので彼女には目を瞑ってもらい、その手を七燈が引いて山を登った。



もう目を開けていいですか?


と夕鶴が期待に胸を弾ませて何度か尋ねてきたが、



まだだ


と彼は悪戯っぽく笑って誘導した。
目的地に到着すると、彼は夕鶴の手を放して言った。



もういいぞ


夕鶴がゆっくりと、確かめるように瞼を持ち上げていく。
刹那――――



……わあっ……


感嘆が漏れる。
彼女の目に飛び込んだのは、満天の星空だった。



町で見るのとは、また違って見えるだろ?





ええ、本当に……


きれい、と胸の声がそのままに開いた唇から零れ落ちる。うっとりとした響きは、彼女がすっかり星空に骨抜きにされてしまったことを伝え、七燈を嫉妬させた。



その顔が見たかったんだが……こうも夢中になられると、少し妬けるな


星を浮かべた瞳が憎らしい。しかし、その横顔は一段と美しく映り、胸の辺りがむず痒くなった。
七燈は首の後ろを軽く掻いて左腕で夕鶴の肩を抱き寄せた。不意のことで驚いた彼女が七燈を仰いだが、彼は空を見つめたまま告げる。



この景色をあんたに見せたかったんだ





……はい


穏やかな声が返る。
腕の中の夕鶴へ視線を移すと、彼女は七燈を見つめて微笑んでいた。先程まで星を浮かべていた瞳には、いまは七燈の姿が映っている。
二人はどちらからともなく顔を近づけ、口唇を重ねた。瞬く星の姿が喝采を送り、祝福しているように見えたのは、奇しくもこの日が七夕の夜だったからである。
天の川はさらさらと静かに流れている。空には雲一つなく、雨が降る気配もない。



今頃、織姫と彦星はここ数年ぶりの逢瀬を楽しんでるんだろうな


昨年は雨だった。その前の年も、そのまた前の年も、生憎の雨模様で二人は川を渡ることができなかった。しかし、今年は運良く晴天となり、無事に川を渡れた二人は再会を果たしたことだろう。
ふふ、と夕鶴が小さく笑った。



わたし達と同じですね


そう照れ臭そうに告げて目元を緩めた彼女の姿に、言い表せぬほどの愛しさが込み上げてきたのをとてもよく覚えている。



送っていただいてありがとうございます


女は丁寧に頭を下げて礼を述べた。背を覆っていた黒髪が所作に沿ってさらりと流れ、御簾のように胸の前に降り彼女の顔を隠す。
七燈はおもむろにその髪を払い除け、彼女の顔を覗き込もうとして――――やめた。良心が咎めたのだ。



……


出しかけた右手を引っ込めて彼は女から顔を背けた。伝えたいことはたくさんあったが、ひとつを口にすれば止まらなくなってしまうことがわかっていたので、全部押し殺して冷たい一言を放つ。



今日のことは忘れろ


女が顔を持ち上げ、不思議そうに首を傾げる。



どうして、そのようなことを仰るのですか……?


寂しそうな声音が夜の静けさに溶ける。振り向かなくても彼女がどんな表情をしているのかがわかった。だから、余計に顔を見ることができず、そのまま七燈は背中を向けた。
左胸が悲鳴を上げている。本当はいますぐ彼女を抱きしめて愛を囁き、誰の手も届かないところへ攫っていってしまいたい。けれども、それはできないのだ。彼女との縁はここで絶たねばならない。そうしなければ、また同じ悲劇を繰り返すだけである。



俺は鬼だ。俺達は妖だ。人間のあんたとは、生まれも、育ちも、住む世界も違う


本来なら、出会ってはいけなかったのだ。恋をしてはいけなかったのだ。
いけないことをしてしまったから、天罰が下った。
そして、悲劇になった。
彼女にとって七燈との出会いは、不幸でしかなかった。
幸せにしてやることは、七燈には初めから無理だったのだ。



――――二度と俺達に関わるな。それがあんたのためだ


彼女への感情を押し殺して吐き、立ち去ろうとする。
その袖を女が遠慮がちに引いて止める。




……


言葉はなかった。何かを言わねばと、言おうとしているのは空気でわかったが、とりとめない音が開いた口から零れるだけだった。
七燈は後ろを振り返らずに女の手を振り解いた。ここで顔を見てしまったら決心が鈍る。
もう二度と、あんな思いはしたくないのだ。
今度こそ彼女が幸せになれる未来を選択したい。
例え、彼女がそれを望んでいなくても。
これがただの自己満足なのだとしても。
惚れた女には生きて幸せになってほしい。
だから、



さよならだ、夕鶴


心の中だけでそっと別れを告げて、彼は飛び立った。
翌日。
失った恋の痛みと独り寝の夜の寂しさに打ち震えながら眠れない夜を明かした七燈の前に、それは何食わぬ顔で現れた。



おはようございます、七燈さま





……は?






おはようございます、頭!! 朝飯の用意はできてますよ! 早く顔洗って、歯磨いてきてください! あ、着替えは出しておいたんで、ついでに一っ風呂浴びてきてください! 昨夜、そのまま寝入っちゃったじゃないですか。酒のニオイがぷんぷんしてますよ~。臭いと夕鶴さまに嫌われちゃいますからねっ


佐々が、まるで女房のように、母親のように身の回りの世話を焼いてくれるのはいつものことで、ずぼらな七燈はそれをとても有り難く思っているが、ここは一発拳骨をくれてやらねばならないところである。




痛あっ





一発で済んだだけ有り難いと思え


で、と七燈は大きな瞳に涙を浮かべている子狸の首根っこを掴んで持ち上げた。




佐々ちゃ~ん、どうしてここにあの女がいるのかなあ? 来ても通すなって言わなかったっけえ?


常の調子で笑いかけたものの穏やかではない心境が顔や声に滲み出ている。
佐々は青い顔をしてぶるぶると震えていた。いつの間にか、尻尾を両手で抱き込んでいる。



まっ……町で、たまたま会って……頭に会いたいって言うから、連れてきたんですっ……


佐々の目から大粒の涙が零れ落ちる。傍から見れば、いい歳をした大人が幼い子供を恫喝しているようだ。黙って成り行きを見守っている女の目にも、そう映っていることだろう。



……ちっ


七燈は舌打ちをして佐々を解放した。彼を責めても仕方がないことはわかっている。こう見えて夕鶴は我の強い女なのだ。対立したときは決して折れず、譲らず、妥協せず、やんわりと己の主張を押し通す。七燈も何度折れたかわからない。
その彼女に頼まれてしまっては佐々も断りづらかっただろう。でなければ、彼が七燈の言いつけを破るはずがない。
佐々はほっと胸を撫で下ろして緊張を解いた。が、それも束の間のことに過ぎず、今度は後ろから女に抱き上げられてしまう。
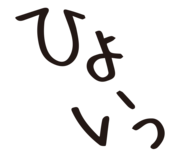



ゆ、夕鶴さまっ?





佐々ちゃんを責めないであげてくださいね


女は彼を両腕に抱いて胸に寄せた。佐々の顔が胸の間に埋もれる。
我知らず、七燈は顔を顰めた。



わたしがわがままを言って連れてきてもらったのです。佐々ちゃんは親切にしてくれただけですよ。何も悪くはありません。お叱りならわたしが謹んでお受けしましょう


嫋やかな微笑みを向けられて七燈は、うっと言葉を喉に詰まらせた。この顔に過去、何度も押し切られてきたことを思い出す。それと同時に、何度も味わった後悔と心傷に胸を抉られる。



もう、あんな思いはしたくない……俺はもう二度と、夕鶴を失いたくない!


また会えた、それだけで十分だ。今度こそ、彼女には生きて幸せになってもらいたい。



その隣に俺がいなくても……


彼女が幸せでいてくれるなら、生きていてくれさえすれば、悲劇にはならない。
いつか寝物語に聞いた、ロミオとジュリエットのような悲劇には。
七燈は一度、目を伏せた。三つ数えながら彼女への想いを底の方へ沈め、再び目を開けたときには何の未練もなく、感情もなく、手酷く彼女を突き放すつもりだった。
しかし、彼の様子から何かを感じ取ったらしい女に先を越されてしまう。



もう一度、あなたに会いたかった





……!


――――数瞬、呼吸が止まった気がした。
目を見開いた七燈の、まるで泣き腫らしたように赤い眼をじっと見つめて女が告げる。



あなたをお慕いしています


沈めた想いが水底からこぽこぽと急速に浮上してくる。過去に沈めた分も一緒に、新たに生まれた想いに押し上げられていまにも溢れ出してしまいそうだ。
飲み込めど、飲み込めど、競り上がってくる。



ッ……


七燈は両手で口を塞いだ。開いたら、全部溢れてしまう。彼女への、夕鶴への、尽きない恋情が延々と流れて辺り一帯に大海を作るだろう。それでも想いは尽きないから、夕鶴を巻き添えにしてしまうかもしれない。否、きっとそうしてしまう。
――――ダメだ。
七燈は自身に言い聞かせる。
ここで彼女の想いを受け入れてしまえばどうなるのか、知らないわけではないだろうと。
彼女の幸せを願うのなら、ここは突き放さなければならない。想いを沈めて、心を殺して、いっそ嫌われるくらいに、憎まれるくらいに傷つければ、彼女も諦めるだろう。



七燈さま


強く名を呼ばれて彼は、はっとした。気づけば、夕鶴が正面に立っていて七燈の手に手を添えていた。
振り払わねばならないのに、体が動かない。
ふわりと彼女が笑う。



昨日会ったばかりで何を言っているんだと思われるかもしれませんが、不思議なんです。わたし、ずっと前から七燈さまのことを知っていたような気がして……ずっと、ずっと昔から、あなたのことを好きだった……そんな風に思うのです


穢れも恐れも知らない瞳が心まで覗き込んでくるようで怖かった。
彼女の、何もかもを許すような眼差しに見つめられると、泣きたくなってしまう。
何度も失敗をした過去を、彼女を救えなかった己の罪を、勝手に許されたような心地になる。
何も知らないはずの彼女にも少しは覚えていることがあるのではないかと、勘違いをしてしまいそうになる。
許されるはずがないのに、覚えているはずがないのに、愛しさが止まらない。




かっ、頭、泣いて――――むぎゅっ


衝動のままに七燈は夕鶴を抱きしめた。間に挟まれた佐々が苦しそうに呻き声を零すが、もはや二人の耳には届いていない。




な、七燈さま……?





っ……ふざけんなよ、あんた……俺の方がずっと好きだったっつの


きつく、きつく、夕鶴の背中を抱いて知らしめる。痛い、苦しい、と漏らしても知るものか。夕鶴がいけないのだ。沈めたはずの恋心を引っ張り上げたのだから責任を取ってほしい。



……もう一度、俺に機会をくれ。今度こそちゃんと、あんたを守ってみせるから


夕鶴にとっては何のことかわからない宣言だろう。しかし、彼女は何も聞かずに



はいっ


と頷いてくれた。
夕鶴の細い腕が背中に回される。後ろめたい心まですっぽりと抱きしめられたようで、とても安心する。



……好きだ、夕鶴。嫌だって言っても、もう離してやれねーぞ






望むところです。七燈さまこそ、覚悟してくださいね。わたしはしつこいですよ





知ってる


初めて七燈は彼女に笑顔を見せた。彼女も嬉しそうに笑って、それから二人は何度目になるかわからない、初めての口づけを交わした。
