第三話 きみはそれでも
第三話 きみはそれでも



いつもよりもせり上がった海面は、奇妙に凪いでいる。
とび色の海。一枚の途方もなく大きな羊膜のような水面が、たわみ歪みゆらめく。



ガキの頃、こんな海なら歩いて行けそうだって思ってた


餌をつけずに釣り糸を垂れ、標はぼんやりとそんなことを思う。歩いていくのが、いや、この海を越えていくのが絶対に不可能なのだと、諦めがついたのはいつからだったろう。
十の頃におぼれ死にかけた時か。
その気になればいつでも島から出ていけるとたかをくくっていたが、漕ぎ出した小舟が木端微塵に砕け、無限とも思えるような渦に繰り返し飲み込まれて初めて、標は海が敵だと知った。



ーーーー……


なめらかな水面が孕む、生き物のあがきを完膚なきまでに否定する大いなる海。
標はあの時たらふく水を飲み、きいん、きいんと警告音のようになり続ける耳鳴りを聞いた。
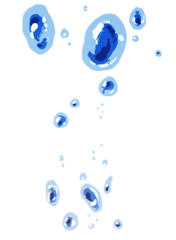



------------


やがてそのすべてが収まって絶対の静寂になり、最後のあぶくがすうっと頭上に上がって行くのを見送って、全身の力を抜いたのだ。
気が付くと甲板の上で、身体には投網がかかっていた。自分の上には親父殿が馬乗りになり、めきめきと胸の骨を折りまくりながら心の臓を蘇生させていた。



ここから出るのを諦めたのは、あの時か?


違うな、と、標は大きく息を吸った。
きっかけは確かにあの時だったかもしれない。だがそれから、少しづつ、少しづつ、海の波が砂をさらっていくように、標の中のまことが削り取られていったのだ。
この島の鬼が減っていることを、年寄りに聞かされた時。



おっかあーーーーー!!





おとうーー、元気でーーー!!


先祖がえりを起こし、普通の人間の見てくれに戻ってしまった幼馴染の何人かが、泣きながら桃太郎の小舟に乗せられていくのを見送った時。



……………。


堤が、先祖がえりを恐れて自分の肩を抱き、竈の隅で震えているのを見た時。



フーーーーーー


親父殿が、疲れ果てた顔をしながら妾の臥所に入っていくのを見た時。



ぼん、分かっていらっしゃいますね。
本当なら一日も早くぼんが嫁を取り、生粋の島人を増やしていかなけりゃならないんです


焦げた髪の一部をじゃきりと切りながら、堤は静かに言った。



煩い連中は、もう随分前からそのことで族長を責めているんです。
でも、あの方はずっと、ぼんに無理強いをしてこなかった。自分が子を増やしているのだからいいだろうと、そればかり言って抵抗してきたんです


何となく惰性で伸ばしてきた髪が、肩に落ちて肌を刺す。そのわずかな痛みがひどくつらくて、標は目を閉じた。



もし、ぼんが桃太郎を島に上げたらどうなります。
いくら好きあっていても、それだけで済まないことが世の中にはある。
考えて下さい、ぼん。
そんなことをしたら、島の連中は、族長は、何より桃太郎は、どうなります。


誰よりも人間に憧れながら、人間を嫌い恐れてきた島の鬼たち。
自分たちを縛りつける醜い姿を呪いながら、それを誇りに変えていくことで紡いできた島の歴史。
そうした切ないすべてが、標から決意を攫っていく。



気づくと、竿に大きな手ごたえがあった。
目の焦点を戻せば、桃太郎が小舟の上で笑っている。



おーーーーーい


今日は大胆にも釣り糸の先端を持って、ぴんぴんと指先で引っ張っていた。



髪、ちょっと切ったんだね。似合うよ


いつもの調子で歯を見せ、楽しそうに笑う。
会うたびごとに美しくなるとは思っていたが、今日の桃太郎はずるいほど綺麗に見える。
光の加減で紅色に輝く髪をまっすぐに流し、前髪は切りそろえ、草色の飾り紐でゆるく横髪を束ねている。日の光にいくら当たっても焦げない白い肌が、よく晴れた青空の中で雲のように映えていた。



ねえ、あんたの親父さん、どうしちゃったの


あくまでも笑い飛ばすような明るさで、桃太郎は言った。



いきなり伝書の鴎が来て、母船で来いなんて言うんだよ。
ついては元島人だった連中と、白犬の跡取りを引き連れて来いって。
おかげで、母船に小舟積んできて、こうやって別行動しないとここにこれなかったんだからね。
一体何事なのよ?





そのままだ


標は一本調子の声で言った。



母船で来いって言ったのは、
いつもの小舟じゃなく
大型の舟に詰め込めるだけ金銀財宝を詰め込んでやるためだ。
犬の跡取りを呼んだのは、
お前をくれぐれも頼むと言い含めるため。
島人だった連中を呼んだのは、
本当にこれが最後の逢瀬になるからだ。


桃太郎は傷ついたふうでもなく、鼻でせせら笑った。



何それ、全然意味わかんない。
っていうか、ちょっと褒めてくんない?あのでっかい舟、岩にぶつけないようにここまで操ってくんの本当に大変だったんだから。





まああれだよね。
あたしの天才的な舵の腕があったから来れたって感じだよね。
ってか、今気づいたけど帰りのほうが舟重くて大変じゃん。
標、もうこういうのナシにしてもらいたいってあんた親父さんに……





うるせえ!


標は強く竿を引いた。しかし桃太郎は釣り糸を離さず、ふたりの間で糸が音をたてて張りつめた。



聞こえてんだろ。この先はないって





意味わかんない





じゃあ何度でも言ってやる。
この先はねえ。
お前がここに来るのは今日が最後だ。


標が竿を斜めに引くと、桃太郎ごと小舟がゆるりと動き出した。
前のめりになりながらも、桃太郎は握り込んだ釣り糸を離さない。



お前らが帰ったら、潮目にくさびを打つ。
渦んなかに大岩をいくつもぶっこんで、堤防を作るんだ。
おまけにいくつかの水門を開けて、潮の流れを大きく変える。
これがどういうことか、お前なら分かるだろ。


島を巡る複雑怪奇な海流は、それそのものが巨大な迷路だ。
正しい道筋を選ばないと、舟は猛烈な加速とともに岩にぶつかって砕け散る。
初代桃太郎に口伝されたのは、正しい迷路の解き方だった。百年近く変わらなかったその海路が、明日から大きく変化する。そうなれば、桃太郎はこれまでのように島に近づくことは出来ない。
母船では今、宴が催されている。白犬の跡取りは、この事実を族長の口から直接聞いているだろう。



この島はまた新たな潮の迷路に取り囲まれる。
そうなると、もう桃太郎は宝の地図を持っていないことになる。
あの娘はただの小娘でしかない。





…………。





それでもつけ狙う奴は後を絶たんだろう。
お前さんがお嬢を一人の女として守ってやるしかない。
白犬の跡取りよ。
頼んだぞ。





命に代えても。





ばっかじゃないの


なのに、彼女は歯を見せて笑うのだ。



あたしは潮がどうなろうと関係ない。
あたしの舵とりの才能を甘く見てんじゃないわよ!


この浅はかな女は、海の内側がどんなに恐ろしいものかも分からず、この島の人々が何を抱えているかも分からずに、あっけらかんと笑うのだ。



人の気も知らないで


標は苛立ちとともに力任せに竿を引いた。
小舟が船足を速め、岸に近づく。



!!


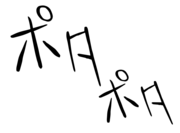

距離が縮まると、桃太郎の掌からぽたぽたと血がしたたり落ちているのが見えた。



ねえ、標


小舟に立ちながら、桃太郎は見たこともないような女らしい微笑みをこぼした。
いっぱい涙をためた瞳に、太陽の光が反射している。



引っ張り上げてよ。
島に上げてよ。ねえ


手からいく筋もの鮮血を滴り落としながら、桃太郎が両手を大きく広げる。
今や小舟はその先端を岸壁に当てている。
標が岸から身を乗り出して、その小さな手を捉えれば、やすやすとこの島に彼女を引き上げることが出来る。



…………





…………


もう一度、乞うように桃太郎が両手を差し向けた。
標は身を傾けたが、唇をきつく結んで竿を引いた。
今度はあっけなく釣り糸が手元に戻ってきた。
それまで息を詰めていた風が、溜息のように吹き抜けた。



標のばか


そう言った桃太郎の声は存外明るかった。泣いているのか、笑っているのか、もう彼女に背を向けた標には、判別することはできない。



またね!


その声を聞きたくなくて、標は足早に岸壁を離れた。



……くっ……!!


途中で、自分が全力で走っていることに気づいた。
蹴躓いて転び、したたかに顔をぶつまで、標の足は止まらなかった。
どこをどう走ってきたのか、まるで記憶がない。心臓がはち切れそうなくらい早く脈うち、息が上がりきっていることすら、まるで他人事のようだった。



ーーーー…ッぉおおおぉぉぉぉ!!!!!


無様で、情けなくて、標は土に顔を埋めて吠えた。
